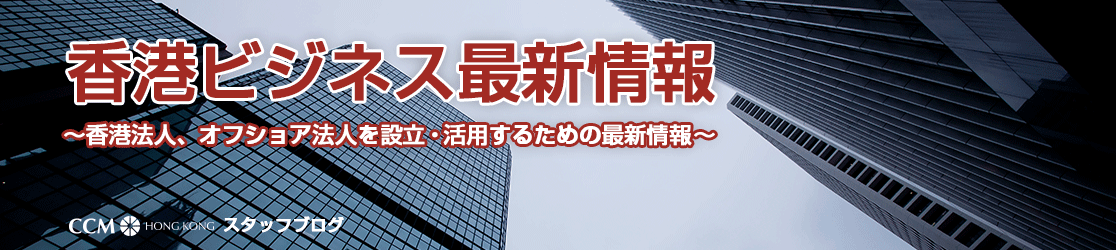【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、租税に関する制度を調査審議する機関となるのですが、この機関が発表した「平成26年6月 法人税の改革について」では、OECDから公表された「BEPS行動計画」(BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)を踏まえて、国際的な租税回避を防止し適正な課税を確保するためわが国の国際課税制度についても、見直しを検討すべきであるとしております。
今回はこの”租税回避”に関して、節税、脱税、そして租税回避等を含めて3回に渡ってご案内させて頂きます。
◆ 節税
所謂、『節税』とは、合法的に租税負担の軽減を図る行為のことを言います。
合法的に経費の増加を図ることも『節税』ですし、税法上、選択可能な所得計算等について、納税額が少ない方法を選択することも『節税』に該当します。
税法上、選択可能な所得計算等の方法の一つに、外国税額控除があります。日本の法人が十分に所得を有している場合には、外国税額控除を適用することにより、日本の法人税の納税額は少なくなりますが、欠損で外国控除が十分にできない場合には、納付した外国税額を損金に算入した方が、結果的に納税額を少なくできる場合があります。
このように『節税』は、税法上認められた範囲内での租税軽減のための対策です。また、選択した『節税』の方法の良し悪しによっては、納税額に大きな差異が生じることになりますので、税務対策として節税策については十分な検討が必要でしょう。
但し、合法的な租税対策として選択した方法であってとしても、その租税対策の前提となる”事実関係”と”実際の事実関係”とが異なる場合には、税務当局からそれらは『節税』と言う解釈ではなく『脱税』であるとの認定がなされる可能性がございますので注意が必要です。
次回は脱税と租税回避に関してご案内させて頂きます。
■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-

-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
-
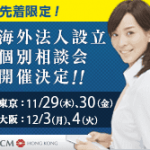
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-

-
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …
-

-
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場
ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …
-

-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-

-
またまた登場?来年度から導入が噂される「新出国税」
先月の26日、日経の紙面には日本の観光庁が新たな出国税を導入する検討に入ったとの …
-

-
香港の国際競争力の“低下”について
スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …
-

-
【中国から撤退をするには?】
中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …
-

-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
-

-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
- PREV
- 【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
- NEXT
- 【日本の税制調査会の動向(2)】